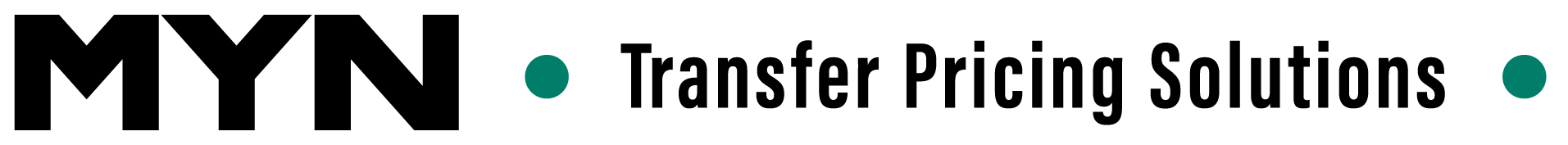「寄附金」とは、一般に無償で財産を相手に与えることといったイメージかと思います。
民法(民法第549条)では、一方(贈与者)が「財産をあげます」と意思表示し、相手(受贈者)がそれを受け入れることで成立するものとされており、概ねイメージ通りの内容になっています。税務上の寄附金も基本的には同じ考え方ですが、より広い範囲を含みます。
たとえば次のようなケースも寄附金とみなされるため、実務上留意が必要になります。
- 金銭や資産を無償で提供する場合
- 無償でサービス(役務)を提供する場合
- 安く売る(低廉譲渡)、高く買う(高価買入れ)
- 債権を放棄したり、債務を免除する場合 など
つまり、税務上の寄附金は「お金をあげること」に限らず、経済的利益を無償で相手に与える行為全般を指します。そのため、グループ会社間だし、ということで提供した出張支援など、会社にとっては思いがけない場面で課税が発生するようなケースもしばしば目の当たりにします。
会社は本来、利益の最大化を目的に活動しているため、通常は経済的な見返りのない支出は行いません。したがって、もし事業と関係のない支出を費用(損金)として認めてしまうと、企業が恣意的に利益を減らして税金を少なくすることができてしまうことになります。
法人税は「事業活動によって得た利益」に対して課される税金です。そのため、反対給付(対価)を目的とせず、経済合理性のない支出や利益の供与を行った場合、それは基本的に寄附金として損金に算入できない(=経費にならない)とされています。
特に、海外のグループ会社(国外関連者)に対して無償で利益を与えるような場合は、その支出は損金にできず、相手が得た利益分を日本側で益金として加算する取扱いになります
(租税特別措置法第66条の4第3項・事務運営指針3-20)。
もっとも、法人税法第37条では、国内の寄附金については、所得や資本金の規模に応じて一部損金算入を認めています。しかし、平成22年度の改正で次のようなルールが定められ、グループ内・海外向けの寄附金は経費にできないことになっています。
- 完全支配関係(100%子会社など)に対する寄附金 → 全額損金不算入
(受け取った側の法人でも、その受贈益は益金不算入) - 国外関連者に対する寄附金 → 全額損金不算入
法法 第37条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
寄附金の概念
税法上、寄附金の概念は法法第37条第7項及び8項で定められています。以下ではこの2項のポイントを見ていきます。
法法 第37条7項
前各項に規定する寄附金の額は、①寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、②内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(③広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における④当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
法法 第37条8項
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、⑤その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
※下線は筆者による
①名目は問われない
寄附金として損金不算入となるかどうかは、名目や科目ではなく取引の実質で判断されます。
したがって、「寄附金」「拠出金」「見舞金」など、どのような名称であっても、また、損益計算書上の勘定科目(たとえば交際費・雑費など)にも関係なく、内容的に寄附とみなされる取引であれば損金不算入(経費にできない)になります。
②金銭や資産の支出に限定られない
寄附金の範囲は、「金銭その他の資産や経済的利益の無償供与」と定義されています。したがって、単にモノやおカネを渡す場合だけでなく、以下の例ように、反対給付(対価)を伴わない経済的利益の提供全般が寄附金に該当します。
- サービスを無償で提供する(役務提供)
- 技術やノウハウを無償で提供する(技術供与)
- 安く売る・高く買う(低廉譲渡・高価買入れ)
- 債権を放棄する、債務を免除する
③経済合理性のある贈与又は無償の供与は除かれる
②の一方で、無償や低額であっても経済合理性が認められる支出は寄附金には該当しません。
たとえば次のようなケースです:
- 広告宣伝費(例:販売促進のために代理店の広告費を負担)
- 見本品の提供(例:新製品の販促)
- 交際費・接待費(例:取引先との関係維持)
- 福利厚生費(例:社員のモチベーション向上)
これらは直接的な対価がなくても、間接的に利益を生む経済合理性があるため、必要経費として損金算入が認められるケースがあります。ただし、社会通念上「過大な金額」や「合理性を欠く支出」は寄附金と判断される可能性があり、際限なく除外されるわけではありません。
また、子会社の整理・再建のための支援(例:債務免除・無利息貸付)も、親会社にとっても経済合理性がある場合には寄附金に該当しないとされています(法通9-4-1、9-4-2)。
ただし、過去の判例でも再建支援の損失負担が寄附金から除外されるには厳格な要件があるため、慎重な判断が必要です。
④寄附金の額
寄附金の額は、上記の通り「当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」と規定されています。したがって、寄附金の額は寄附をした時点の時価(市場価値)を基準として計算します。具体的なイメージとしては、以下のような額が各ケースにおける寄附金の金額になります。
- お金をあげた場合 → その金額
- 物や資産をあげた場合 → 贈与時の時価
- サービスや技術を無償で提供した場合 → その経済的な価値(相当額)
税法上、「贈与の時点における価額(時価)」や「供与の時点における価額」の具体的な算定方法までは明記されていません。そのため、実務上は例えば次のように考えて、対応を図ることになります。
- 市場価格や相場があるもの → その時点の市場価格・時価情報を利用
- グループ企業間契約などで価格が決められている場合 → 契約で定められた金額を「確定債権」として扱う(その金額を回収しなかった場合、その未回収分が寄附金の額になる)
- 相場や契約がない場合 → 提供した資産や役務の原価(コスト)を時価とみなして算定
要するに、寄附金の金額は「その時点での経済的価値」を基準に判断され、「いくらで提供したか」ではなく「本来いくらの価値があったか」で評価されるという点がポイントです。
⑤低額譲渡も課税対象
寄附金として損金不算入となるのは、無償で財産を渡した場合だけではありません。
時価よりも低い価格で資産を譲渡した場合にも、その時価と実際の譲渡価格との差額が寄附金として扱われます。
つまり、
「その譲渡時点の時価 - 実際の販売価格 = 寄附金の額」
となります。
税務上は、譲渡した時点の経済的価値(時価)を基準に、企業が実質的に相手にどれだけの利益を無償で与えたかを測り、その部分が経費にできない寄附金扱いとなります。