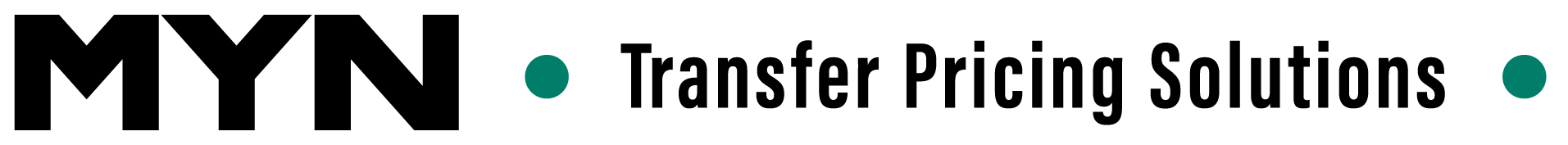日本における移転価格税制の特徴
移転価格税制の起源は、1921年の米国内国歳入法典(IRC)にあるとされています。移転価格の問題は当時から世界的に認知されてはきたものの、世界大戦もあり、また問題の軽重や処理能力が各国で異なることもあって、世界的に見れば2000年代ころまでは制度導入の状況も国・地域によってまばらで、細則が設けられない中での執行や、独自の制度設計も散見される状況が続いていました。
2024年現在、いまだ独自の執行がみられる国などもありますが、特にOECDが中心となって2012年に立ち上げられたBase Erosion and Profit Shifting(BEPS)への対応プロジェクト(所謂、BEPSプロジェクト)以降は、多くの国・地域を巻き込んだルールの統一化が進められている状況です。
そこでこの記事では、世界的な移転価格税制の変遷を外観するとともに、日本における移転価格税制の特徴についても解説を試みたいと思います。
この記事の要旨
- 世界的な移転価格税制の歩みの中で日本はグローバルスタンダードな制度設計を企図している
- 日本の移転価格税制は比較的長い歴史を有しており、OECDと足並みを揃えつつも、寄附金規定という独自の考え方もある。そのため、税務調査等の場面では、移転価格税制と寄附金規定のいずれの適用を受けるかも、実務上重要な論点になる
移転価格税制の歩み
親子会社をはじめ、同じグループ内の企業の間では、相互に独立した企業の間、すなわち独立企業間の取引では通常設定され得ないような対価が設定されることがあります。それは、例えば、子会社を支援する目的で行われることもあれば、特定の国外市場で商品の浸透を図るために行われることもあり、あるいは第三者向け価格はインフレなどを考慮して随時改訂しているにも関わらず、グループ会社向けの取引は改訂を失念してしまった、といったケースもあるでしょう。
同じグループの企業、すなわち関連者間の取引は、国内でも主に地方税の観点から問題になることはありますが、国を跨ぐ取引になると、その影響は通常相手国との関係の中でより一層複雑かつ影響が大きくなります。端的に言えば、対価が歪みは各国に配分される所得、ひいては税額に帰結するので、国と国との間の税の取り合いの問題に発展します。実際、市場や経済活動のグローバル化とともに、企業の多国籍化が進展する中、グループ内の国際取引に係る上記の問題は無視できないものとなりました。いわゆる移転価格税制はそのような問題に対処するために生まれた税制です。
移転価格税制の起源は、1921年の米国IRC第240条(d)項に求めることができるとされ、米国親会社の経理操作により、外国子会社が親会社の利益の圧縮、歪曲する行為を防止することを目的としたものであったと言われています(遠藤克博「移転価格税制と寄附金課税」(1999))。米国ではその後も改正を重ね、1943年には概ね現行法(IRC第482条)の形になったとされていますが、移転価格税制の概念はやがてOECDモデル条約9条にも反映され、その他にも1979年以降に公表・改訂が続けられているOECDガイドラインや2012 年 10 月に国連・税の国際協力に関する専門委員会が公表した「途上国のための実務的移転価格マニュアル」などを通じて、今日では米国以外の世界各国に広く認知されるに至りました。
移転価格の概念は概ね世界で共通している一方、その歴史や細則は各国各様です。日本は調査又は事前確認審査の執行にあたって、OECDガイドラインを参考にすることとされるなど、基本的にはグローバルスタンダードな制度設計になっていると言って差し支えないでしょう。とはいえ、特徴的な部分もあるため、本稿では主な特徴の理解にあたり、参考になる情報を提供できればと思います。
日本の移転価格税制
日本における移転価格税制の導入は昭和61年(1986年)の税制改正に遡ります。中国は1991年、インドは2001年、タイは2002年、マレーシアやベトナムは2003年に移転価格税制を導入したとされていますので(宮地秀門「主要アジア各国の移転価格税制等とその執行の現状」税大ジャーナル 2(2005))、日本は特にアジアの中では移転価格について長い歴史、そして経験を有する国であると言えます。その分、紆余曲折を経てきたともいえるでしょう。もっとも、歴史の振り返りよりも、現行法をベースにその特徴を記した方が実務に役立つと思いますので、そのような観点からいくつかポイントを書いてみたいと思います。
OECDと足並みを揃える日本の移転価格税制
タイトルの通り、日本の移転価格税制はOECDにおける議論や合意内容と足並みを揃えながら徐々にその形を変えてきました。そのような対応を図る国は必ずしも珍しくないため、これが日本の特徴の一つと言えるかというと議論があるかと思います。しかしながら、移転価格税制の元祖ともいえる米国がOECDでの議論にとらわれず制度の発展をリードしてきたことや、欧米諸国と利害を異にする中国やインド等が一部OECDガイドラインとは異なる制度構築を図ってきたことを考えると、日本の移転価格税制の特徴の一つに挙げても良いのではないかと思います。
日本の移転価格税制におけるOECDガイドラインへの直接的な言及は、法令上はなく、当局の内部事務執行に係る統一的なルールに当たる移転価格事務運営要領(事務運営要領)にみられるのみです。しかしながら、例えば、日本の移転価格文書化制度は、OECDが中心となって2012年に立ち上げたBEPSプロジェクトで勧告された行動計画を反映する形で、平成28年度(2016年度)の税制改正を経て刷新されています。ちなみに、BEPSプロジェクトを立ち上げたOECD租税委員会の当時の議長は日本の浅川財務省財務官であり、この事実からしても、日本のOECDへ関与の強さが伺い知れるかと思います。
上記のほかにも、令和元年度(2019年度)税制改正では、やはりOECDでの議論を受けて、無形資産の定義の明確化、DCF(Discount Cash Flow)法の移転価格算定方法への追加、所得相応制基準の導入なども図られたほか、過去には日本独自の簡便法なども認められてきた金融取引についても、改正事務運営要領により独立企業原則を重んじる形に改められ、また2024年4月1日以降開始事業年度にはグローバル・ミニマム課税に対応する制度が適用されるなど、OECDに足並みを揃える姿勢を貫いています。
2023年7月12日、OECDは経済のデジタル化から生じる課税上の課題に対応するための二本柱の解決策に関する成果声明を公表しました。これはBEPS 2.0プロジェクトの第1の柱と第2の柱に関する包摂的枠組みに参加する143カ国のうち138の国と地域の合意を反映した声明とされています。合意した国・地域のGDPの合計は、全世界のGDPの90%以上を占めるとされているため、まさにグローバルスタンダートとなる合意事項と考えて良いでしょう。その後もさらに、2024年2月19日にはOECD/G20BEPS包摂的枠組会合(IF)が所謂Piller1(第1の柱)の利益Bに関する報告書を公表するなど、議論は進展しています。
日本政府は上記のような直近の議論もタイムリーに追いかけています。今後も、OECDと足並みを揃えた制度の新設・改訂が行われていくでしょう。
寄附金課税の存在
日本では、寄附金の損金算入には厳しい制限が設けられています(以下、関連法令等を便宜上「寄附金規定」とします)。日本の税法おける寄附金の概念は比較的広く、慈善事業で個人や組織・団体に贈った金銭といった一般的なイメージのものだけでなく、移転価格税制で問題となる海外のグループ会社、すなわち国外関連者に対する寄附金についても、その損金算入範囲について税法の制限を受けることになります。
寄附金規定に関する詳細は別の記事に譲りますが、寄附金規定は、端的には下表の通り、移転価格税制を近接する分野でありながらも、一部、それとは異なる特徴を有する規定として機能しています。この点は、寄附金課税というものになじみがない皆様はもとより、なじみがあっても移転価格税制と関連性があるものと認識されていない皆様にとっては、お見知り置きいただく価値があるポイントであると考えております。
もう一歩だけ詳しく申しますと、寄附金規定は移転価格税制と同様の所得調整機能、すなわち一定の基準を超えた費用負担等につき全額損金不算入とする機能を有する一方、二重課税の救済措置となる相互協議の申請可否(前者は原則不可)等の点で異なります。
それ故、税務調査の場面などにおいて、寄附金規定と移転価格税制のいずれの考え方が適用されるのかは、納税者にとってしばしば悩みの種になっており、だからこそこの点を認識しておくことは、実務上重要になります。
| 移転価格税制 | 国外関連者 に対する寄附金 | (参考) 一般の寄附金 | |
|---|---|---|---|
| 所得調整の対象 | 独立企業間価格との差額 | 時価との差額 | 時価との差額 |
| 課税される場面 | 内国法人が取引対価を過少に受け取った場合又は過大に支払った場合 | 資産や経済的利益を贈与したり無償で供与したりした場合(例外あり) | 資産や経済的利益を贈与したり無償で供与したりした場合(例外あり) |
| 調整額の取扱い | 全額損金不算入 | 全額損金不算入 | 一部損金算入可 |
| 更正期間の制限 | 7年 | 5年 | 5年 |
| 相互協議の申請可否 | 可 | 原則不可 | – |