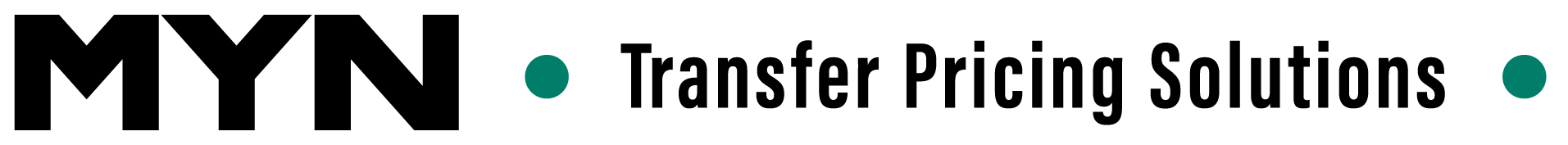移転価格税制は、なじみのない方も多い税務分野ですが、実は日本には昭和61年(1986年)に導入されており、約40年の歴史をもつ税制です。その長い歴史の中で、法令はもとより、執行のトレンドも変化してきました。
ビジネスのグローバル化、そしてデジタルエコノミーの隆盛などを受けて、移転価格分野の国際的な議論はますます活発に行われ、近年ではBEPS(Base Erosion and Profit Shifting。税源浸食と利益移転)ないしBEPS2.0といった文脈で、移転価格やその周辺分野に関する国際的な議論も取り沙汰されるようになりました。
変化を続けてきた移転価格税制ですが、一方で変わらない部分もあります。それは、移転価格税制が多様なビジネス・取引を対象にした国・地域間の利害が複雑に絡む所得配分に関するルールであり、それゆえ”解釈”や”判断”が交錯するグレーゾーンが多い税務分野であるという点です。
上記のような特徴を受けて、実務も変遷してきました。以下はあくまでイメージですが、これまでの移転価格の歴史と実務の大きな流れを綴っています。
黎明期
移転価格税制が導入されて間もない頃は、やはり大手多国籍企業が調査のターゲットでした。また、企業の移転価格対応の指南役は、やはり税務の専門家、とりわけ高度なクロスボーダー案件を得意とする大手会計事務所が主に担ってきました。当初は(国税出身者を含む)税理士、公認会計士の専門家が多かったと思われますが、“価格”というあいまいなテーマを扱う税制であることもあり、国内会計事務所の移転価格チームには、経済学のPhDや弁護士、移転価格税制を世界に先駆けて導入した米国実務経験者、コンサル出身者なども参画するようになりました。
制度理解の浸透も十分とは言えない中、今以上にルールがあいまいだったこともあり、数百億円規模の更正事案もしばしばみられました。そうした中で判例や裁決事例が徐々に積み上げられていきましたが、制度導入後しばらくは納税者の主張が受け入れられることはまずありませんでした。
浸透期
事前確認(APA)制度の活用により、マーケットリーダークラスの大企業を中心に、移転価格リスクの低減が進みました。APAの最初の合意事案は1990年代初頭のものと言われています。また、いわゆるアドビ事件(東京高判平成20年10月30日税資258号順号11061)のように、納税者全部勝訴事案も見られるようになりました。
デジタルエコノミーの発展も相まって、世界的に高度なタックスプランニング事例もみられるようになりました。当初から扱いが難しかった無形資産は一層、実務においても問題になるようになりました。それに応じて、日本でも費用分担契約(CSA)の導入や、残余利益分割法(RPSM)による分析を前提にした移転価格対応実務も「めずらしい」と言われながらも、増えていきました。
また、守りを固めた大企業をターゲットにした調査事案は数を減らし、中堅・中小企業に対する調査が増えました。黎明期に比べると全体の課税額は如実に減りましたが、中小・中堅企業にとって、どのように説明・抗弁したら良いかもわからない分野での寝耳に水のキャッシュアウトは非常に大きな問題になります。では、中堅・中小企業の移転価格実務は誰が担うのか?社内での知見醸成には限界がある中、専門家は大手会計事務所に集中しており、予算感に合う形で対応を担える専門家は今でも多くない状況です。
ポストBEPS期
コーポレートインバージョンを利用した租税回避は1980年代にもみられましたが、税制の網目をかいくぐるようなタックスプランニングを一般消費者にも良く知られているGoogleやApple、スターバックスといった企業が活用していることが一般紙でも報道されるなど、社会問題になりました。
こうしたトレンドを受けて、租税回避に向けた国際協調が一層強固となりました。具体的には、2012年6月にBEPSプロジェクトが始動し、2015年には15の行動計画で構成されたBEPS最終報告書が公表されました。
BEPSプロジェクトでは、実務に配慮したルールの再構築が図られる一方、納税者側にもより多くの情報開示が迫られる流れができました。特に移転価格に関する文書化制度は、日本を含め、BEPS以前から導入していた国も少なくありませんでしたが、ポストBEPSの世界ではより多くの国や地域で導入されることとなり、またCbCRやマスターファイルといった新たな文書の作成が求められる契機になりました。
移転価格実務は、コンプラ色も強くなりました。BEPSプロジェクトを契機にポリシーを改めたり、新たに作ったりするケースもあるものの、特にオペレーションが確立した大手多国籍企業は、法令で求められる文書への対応が新たなタスクとして明確に認識されるようになりました。会計事務所側も文書化実務に対応すべく、一層幅広く人員を登用するようになりました。
移転価格が社会問題化し、調査ターゲットが変容する中、中堅・中小企業の間でも移転価格に関する認知が随分広がりました。専門家不足の中、必ずしもタイムリーに対応を進められるケースばかりではないようですが、コンプラ要請を契機に、社内の体制を整えていくような流れができつつあるように思います。
BEPS2.0(2021年10月以降)のいま
BEPS2.0とは、多国籍企業による租税回避や利益移転の問題に対処するための国際的な取り組みです。詳述は控えますが、ざっくりと申せば課税権を市場国に割り当てる取り組みと、グローバルミニマム課税の導入という2本柱の取り組みです。極めて複雑かつ特に大手に照準に充てた取り組みが目立つところはありますが、移転価格の文脈で広く影響が出ると思われる変化の一つに、利益B概念の提唱があります。利益Bとは、平たく言えば、基本的な販売・マーケティング活動に対する独立企業間原則の適用を簡素化・合理化するための手法で、所定の条件に当てはまる取引について所定の利益率を達成していれば移転価格違反なし、とする考え方です。
日本では当面利益Bアプローチの導入は見送っていますが、BEPS包摂的枠組み(IF)の参加国は、それぞれの国内法等に従うことを条件に、対象管轄区域(CJ)が利益Bアプローチを適用した結果を尊重することとされています。しかし、利益Bアプローチを導入した国・地域はこの簡素化アプローチに基づき移転価格調査・更正を検討することが可能になる一方、そのようなアプローチによる課税に相手国側は拘束されません。そのため、日本を含む利益Bアプローチ非導入国では従来どおりの分析が求められることから、相手国側での利益Bアプローチから導かれる所得配分と異なる結果が導出される可能性が残ることになります。従って、取引相手国側の制度に従来以上に気を配る実務が、当面のスタンダードになっていくことなると考えられます。